2024年に「メンタルヘルス・マネジメント検定試験 二種 ラインケア」という資格試験に挑戦しました。
結果はなんとか合格でしたが、大変お恥ずかしいことに、合格点超スレスレ。笑
そんなギリギリな資格取得でしたが、30代共働き、かつ娘一人の育児をしながらチャレンジした記録ということで、似たような境遇で受験を考えている方がいれば、参考になれば幸いです。
メンタルヘルス・マネジメント検定とは
その名の通り、メンタルヘルスをマネジメントするための知識や方法について問われる検定試験となっています。
大阪商工会議所主催の民間資格であり、公式ホームページでは以下の通り検定試験について紹介されています。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は、働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得していただくものです。
大阪商工会議所 検定試験HPより引用
検定試験は以下の3コースに分かれています。
- 一種(マスターコース)
- 二種(ラインケアコース)
- 三種(セルフケアコース)
それぞれのコースに対象や到達目標が設定されていますが、今回私が挑戦した二種については、公式ホームページにて以下の通り説明されています。
対象:管理監督者(管理職)
目的:部門内、上司としての部下のメンタルヘルス対策の推進
到達目標:部下が不調に陥らないよう普段から配慮するとともに、部下に不調が見受けられた場合には安全配慮義務に則った対応を行うことができる。大阪商工会議所 検定試験HPより引用
部下を持つ人向けのコースですね。今回はこれに挑戦してみました。
受験のきっかけ
勤め先で、部下を持つ職位の社員向けにこの資格が紹介・受験推奨されるタイミングがあり、資格の存在についてはそこで初めて知りました。
社内外でメンタル不調になる知り合いもたまに見聞きしていたため、自分自身や部下も、可能性ゼロじゃないな…と思い、いざという時の適切な対処法、また、そうならないようなマネジメントを学ぶため、受験を決めました。
どんな問題が出るの?
二種の出題範囲は以下の通りとなっています。
①メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割
②ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
③職場環境等の評価および改善の方法
④個々の労働者への配慮
⑤労働者からの相談への対応 (話の聴き方、情報提供および助言の方法等)
⑥社内外資源との連携
⑦心の健康問題をもつ復職者への支援の方法
メンタルヘルスの基礎も含まれていますが、やはり職場環境や他の労働者のメンタル不調への対処が大部分を占めています。
具体的な問題はここには記載しませんが、過去問が書籍で発売されています。また、全問選択肢から回答を選ぶ形式です。
合格ラインと合格率
二種の合格ラインは100点満点中70点とされています。問題は50問なので、35問以上正解で合格となります。
合格率は回によってマチマチですが、50%~70%程度のようです。
ちなみに…ノー勉でも解けそうか?と気になる方もいるかもしれません。選択式ですから、それっぽいのを選んで合格できるんじゃないか、と。
人によるかもしれませんが、私の場合はとても無理だったと思います。
会社で労働安全の実務に関わっていたり、事前に何らかの教育を受けていればいけるかもしれませんが、私はそうではありませんでした。
合格に向け、次のような方法で勉強を進めていきました。
勉強方法
① 書籍でインプット
ほぼ何も知らない状況からのスタートでしたので、まずは参考書を読んで知識を習得することとしました。使用した参考書は、主催の大阪商工会議所が出版している公式テキストです。
7つの出題分野毎に章が区切られており、丁寧に説明が書いてあります。
第一章から順に読み込んでいき、一つずつ理解を深めていきました。
なお、他にも色々と参考書は売っていますが、書店で「自分に合っている参考書は…」とゆっくり吟味する時間など無く、ハズレの無い王道の公式テキストを使って勉強開始した方が効率的、と思い、これにしました。
お時間が取れる方は他の参考書もぜひご覧いただくと良いと思いますが、このテキストも非常に分かりやすく、十分良いものでした。
②アプリでアウトプット
知識定着のため、並行してアウトプットをしましたが、これにはスマホアプリを活用しました。
使ったアプリは「メンタルヘルスマネジメント検定II種 秒トレアプリ」です。
ひたすら問題を解きまくれるアプリで、7つの出題分野毎に出すことも可能です。
使い勝手が良く、スキマ時間にコツコツアウトプットするには最適のアプリでした。
アプリのインストール自体は無料ですが、アプリ内の全ての問題を解けるようにするには380円の課金が必要です(2025年3月現在)。課金する価値は十分過ぎるほどあります!
この2つの方法を軸に、公式テキストインプット→アプリでアウトプット→アプリで分からなかった問題を公式テキストで再確認…といったサイクルで勉強を進めていきました。
日々の取り組みと学習期間
仕事と家事、当時2歳の娘の育児をしながらの勉強なので、まとまった時間はなかなか取れません。
私の場合、まとまって学習に充てられたのは
- 通勤時間(電車)の往復20分程度(週5日)
- 寝る直前の20~30分(平均週2回程度。残業時間や子どもが寝る時間、家事の状況次第で取れない場合も)
でした。これらに加えて、ほんのちょっとした空き時間にはアプリをやりまくっていました。
受験申込から試験日までは4ヶ月程度、総学習時間はだいたい30~40時間くらいだったと思います。
いざ受験!
さて、試験本番は会社にて、団体受験形式で受けました。
試験時間は2時間。50問なので、1問2分少しで解けばOK。
……なのですが、実際2時間もかかりません。
というのも、計算問題のように解くのに時間がかかる問題はほぼなく、「見て、分かるか分からないか」の問題ばかりだからです。逆に言えば、分からないものはどれだけ時間をかけても分からないと思います。
ということで、私の場合は開始40分くらいで会場を後にしました。笑
分からない問題もありましたが、「こりゃ時間かけてもダメだ」というものでしたので、潔く退出。
私より早く出ている人も結構いましたよ。
結果は…
さて、冒頭記載の通り合格はしましたが、スコアはどうだったかというと…
72点!!!
合格基準が70点なので、本当にスレスレでした。笑
大変お恥ずかしい。ですが、一応、合格です。
受験を終えて
資格試験への挑戦は久しぶりでした。独身の頃はTOEICなどを受けていましたが、結婚&子どもができてからは初めて。
夫婦ともに仕事があり、家事と育児を分担する状況での資格試験は、思うように時間が取れないことを強く実感しました。
家事育児のバランスを一時的に妻に傾ける、睡眠時間を削るなどの荒業もありますが、家庭&健康最優先で生きてるので、最初から選択肢に無し。
従って、使える時間をどれだけ無駄なく使うか、に全てが懸かっていました。
今回の挑戦を通して、このあたりのスキルが身に付いたように思います。通勤電車の中では即勉強モードにスイッチできるようになり、ちょっとスキマ時間ができればパッとアプリを開く、そんな習慣が身に付きました。
最後に
今回、共働き&2歳児の育児に取り組みながら、メンタルヘルスマネジメント検定 二種に挑戦し、なんとか合格しました。
簡単ではないですが、時間をうまく使えば、育児しながら資格取ることもできるんだな~と実感。
勢い余って、この後、また別の資格に挑戦しましたので、別の記事で紹介させていただきます。
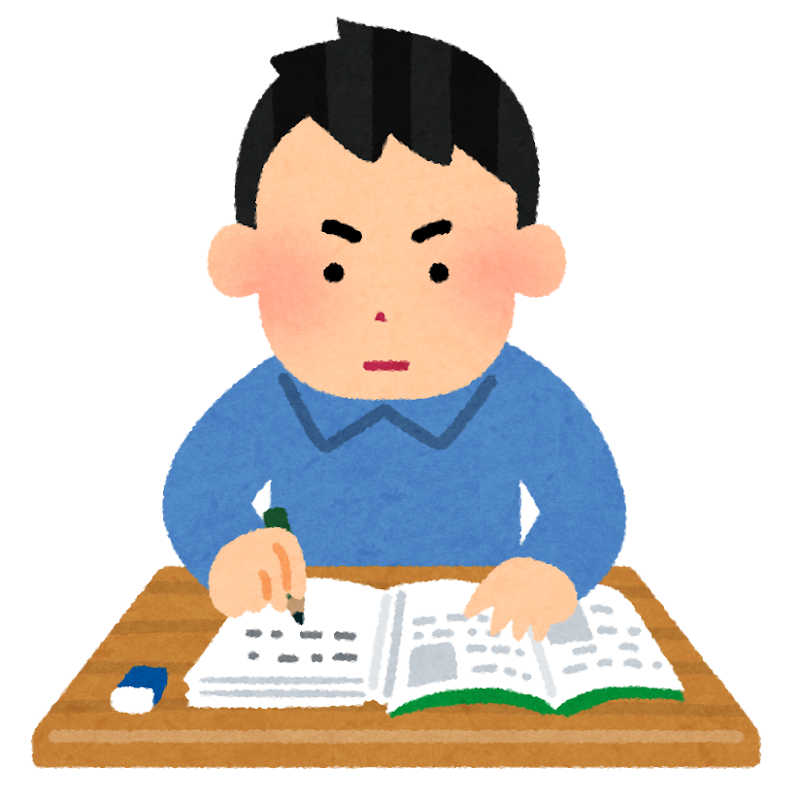



コメント